函館とウラジオストクとの新たな交流 ―文化・学術交流、はじめの一歩―
長谷部一弘
新たな博物館交流の一歩
平成14年7月28日、市立函館博物館と沿海地方国立アルセニエフ博物館との間において博物館姉妹提携がなされた。これは、函館市市制80周年記念、函館・ウラジオストク両市の姉妹都市提携10周年記念事業の一環として行われたものであったが、とりわけ北東アジアの両地域における博物館を媒体とした新たな文化交流のかたちをめざす博物館交流のはじめの一歩となった。
そもそもこの提携にいたる経緯を思い起こせば、平成13年2月に「日本の中のロシアを求めて」を取材するために来函したアルセニエフ博物館の研究員スヴェトラーナ・ルスナク女史(「会報」No.20に寄稿)がロシアとゆかりの深い函館の地に在る函館博物館との博物館交流を提案したことがきっかけであったと記憶している。地域に根ざした博物館をめざす函館博物館は、北東アジアを視野に入れた幅広い博物館活動の可能性を探るものとしてそれを受け入れたわけである。
調印書には、博物館交流の具体的な手だてとして、刊行物等の情報の交換、専門分野における共同研究、共同企画による展覧会、シンポジウム等の開催が盛り込まれ、両博物館が地域の中で先ず出来るところから交流を図っていくことで合意した。函館市青少年研修センターを会場に開催されたガリーナ・アレクシュク館長と金山教育長による調印式に引き続き、ルスナク女史による「函館―ウラジオストク:歴史的関係と協力の展望」と題した記念講演では、およそ150名の参集者を前に函館とウラジオストクにおけるこれまでの歴史的事実と今後の可能性を篤く述べられた。
そしてこの博物館姉妹提携の調印により、早速交流事業の第1回として、平成15年にウラジオストク市において開催される第3回ウラジオストク・ビジュアル芸術ビエンナーレ参加の博物館プログラムノミネートの展覧会「函館とウラジオストク―歴史的関係と協力の経験」を企画、開催することとなった。
博物館姉妹提携1周年記念事業(ウラジオストクで函館を紹介する)
平成15年7月1日から6日の1週間、アルセニエフ博物館を会場に多くのウラジオストク市民を集めて博物館姉妹提携1周年記念展覧会「函館とウラジオストク―歴史的関係と協力の経験」が盛大に開催された。「函館、ロシアの架け橋、その人々」、「函館、ウラジオストクとの出会い」、「目で見る今日の函館」で構成された展示内容は、函館から持参したジュラルミン製ケース2箱分の写真パネル、年表、書籍、観光ポスター、ビデオ映像、CD等の限られた展示資料で満たされた。期間中の新聞報道等のインタビューでは、博物館交流の意義や展覧会の趣旨などにおよんで初めて紹介された函館とウラジオストクとの歴史的関係や函館の街の素顔などに大きな興味と関心が寄せられた。また、この展覧会開催期間中には、沿海地方に在る地方博物館を一堂に会した「博物館円卓会議」が設けられ、文化の相互理解発展に向けた博物館、ギャラリーの役割や博物館と地域の関わりについて活発な討議がなされた。特別ゲストとして迎えられた佐野館長と私は、日本、函館における博物館と地域の関わりについての実態や可能性などを紹介し、共有した情報交換の場を持つことが出来た。ちょうど、平成15年は、「ロシアにおける日本文化フェステバル 2003」にあたり、ロシア各地では多岐にわたる日本文化に触れる機会が設けられ、滞在期間中の沿海地方、日本などの周辺地域を取り込んだウラジオストク市あげての芸術、文化の祭典ビエンナーレでも書道などの多彩な日本文化のプログラムが組まれる中で、博物館交流事業がその一つとして参加できたことも大きな交流の成果であった。私が観た祭典ビエンナーレに沸いた1週間のウラジオストク市民と博物館との関わりは、博物館そのものが地域と市民に当たり前に向き合い、市民も生活の一部として当たり前に博物館を行き来していることであった。
平成16年度函館、ウラジオストク博物館交流事業(函館でウラジオストクを紹介する)
博物館姉妹提携1周年記念事業「函館とウラジオストク」展の成果をもとに、平成16年7月5日から7月11日の1週間、函館市民芸術ホールにおいて展覧会「ウラジオストクと函館」が開催され、函館市民にこれまでのウラジオストク市と函館市との歴史的、文化的交流やウラジオストク市の歴史、文化、姉妹博物館アルセニエフ博物館の歴史などが紹介された。展覧会は、事前の企画準備から展示に至るまでイライダ・バプツェヴァ主任研究員、ライダ・クリメンコ写真所蔵専門員をスタッフとしたアルセニエフ博物館と函館博物館との共同企画・展示によるものであった。
展示に関わる写真パネル、年表、解説パネル、キャプションなどは、双方による資料のリストアップ、事実関係の確認、翻訳、画像処理、校正にいたるまで長距離のFAX通信などで詳細に協議、調整され、両博物館スタッフのほかに、双方の交流に関係する多くの機関や人々の協力によって遂行されたと聞く。このたびの展覧会の開催のためにバプツェヴァ、クリメンコ両女史のアルセニエフ博物館スタッフに加え、ウラジオストク日本センター職員であるオリガ・スマローコヴァ女史が翻訳や通訳の労をとって来函されたことも博物館交流事業の意義を覗かせている。
なお、今回の展示にあたっては前々日の7月3日から、函館博物館、アルセニエフ博物館の職員らと共に、当会の会員もボランティアで展示作業に加わり、実際に汗を流しながら交流を深めることができた(展示内容の一部は当会のホームページで公開します)。
さらに、来函した3人は、展覧会開催期間中、渡島、檜山地方の博物館や教育委員会でつくる道南ブロック博物館等施設連絡協議会の研修会や市民を対象とした展示解説セミナーでの講師参加、ゴローニン幽閉の地松前探訪、そして当函館日ロ交流史研究会の例会でも、特別ゲストとしてアルセニエフ博物館のお話をしていただくなど多岐にわたり交流を深めた。
滞在期間中、ウラジオストクでは、アルセニエフ博物館が博物館姉妹提携の記念日にあたる7月28日より3ヶ月にわたり路面電車を使った移動博物館、つまり博物館電車が昼夜市街を駆けめぐるイベントを展開する計画を準備中であることを聞いた。車内には、昨年アルセニエフ博物館で使用した展覧会の写真パネルや年表、解説パネル、観光ポスターなどが掲げられ、函館とウラジオストクの歴史的、文化的関わりがウラジオストク市民はじめ大勢の観光客の眼に触れられるようだ。走る博物館電車の展示内容にも増して、路面電車という仕掛け装置によって博物館交流の意味やその可能性を地域市民に積極的に訴えていこうとする姿勢に共感するとともに博物館交流の成果が着実にウラジオストクで浸透しているように感じた。
博物館電車のホットな話題を聞いた時ふと、昨年の展覧会終了後、函館博物館で用意した120枚程の展示パネル類をすべてアルセニエフ博物館に寄贈した際、その好意に応えるかのようにアレクシュク館長が、いただいた貴重な写真パネル類を沿海州地方に在るすべての地方博物館の巡回展などによって多くの地域の人々にも是非紹介したいと篤く語っていたことを思い出した。

芸術ホールでの展示作業
「会報」No.26 2004.9.10 2004年度第1回研究会報告要旨
アルセニエフ博物館について
アルセニエフ博物館主任研究員 イライダ・バプツェヴァ
国立沿海地方アルセニエフ総合博物館(以下、アルセニエフ博物館とする)は極東・シベリア地域における最も古い博物館である。現在に至るまでに名称は4回変更された。
1884年 アムール地方地理学協会の博物館として創設された。
1890年 この年一般に入館を開放。19世紀末からF.F.ブッセ、V.P.マルガリートフ、L.Ja.シテルンベルグ、M.I.ヤンコフスキー、V.K.アルセニエフ等の著名な学者の協力により、主に民族学・考古学のコレクションを行ってきた。
1900年 全世界パリ展示会でアルセニエフ博物館の民族学コレクションは銅メダルを2つ授与された。
1925年 ソビエト政府によりアムール地方地理学協会の博物館は、独立した機関となり、名称もウラジオストク国立州博物館に変わった。
1938年 ロシア極東地域で沿海州がハバロフスク地方と沿海地方に分けられた。
1939年 上記の理由でウラジオストク国立州博物館は改組され、沿海地方郷土誌博物館となった。
1945年 ソビエト政府令により沿海地方郷土誌博物館に有名な探検家V.K.アルセニエフの名前を冠した。
1985年 アルセニエフ沿海地方郷土誌博物館が、現在の名称である国立沿海地方アルセニエフ総合博物館となった。
Ⅱ 概要
・国立文化機関 国立アルセニエフ沿海地方総合博物館 ウラジオストク市スヴェトランスカヤ通り20番
・1884年創立。ただし、1890年9月30日に一般の入館者に開放したため、市民にはこの日が本博物館の創立日とみなされている。
・職員数は198名、うち、学芸員・研究者66名
・ウラジオストクの本部のほか、ダリネレーチェンスク市歴史博物館、パルチザンスク市歴史博物館、レソザヴォツク市歴史博物館、アルセニエフ市歴史博物館、チュグエフカ村にある作家A.ファデーエフ文学記念館の5つの支部を沿海地方に有する国立総合博物館。
・ウラジオストクの本部は、街の中央にある本部(スヴェトランスカヤ通り20番)の他、国際展示センター(ピヨートル大帝通り6番)、アルセニエフの家博物館(アルセニエフ通り7番―B)、スハーノフの家博物館(スハーノフ通り9番)の全部で4つの建物を管理し、総面積は2778平方メートルに及ぶ。
・収蔵コレクションは、ロシア極東地域で最大で、自然・歴史・考古学・民俗学・文化関係の40万点以上に上る。毎年、6000点以上の新蔵品が博物館に入ってくる。

研究会の様子

アルセニエフ博物館
「会報」No.26 2004.9.10 2004年度第2回研究会報告要旨
最後の「低い緑の家」 ―サファイロフの晩年―
清水恵
大正末期から昭和初期にかけて、湯川には一群の白系ロシア人が居住した。現在の私の住まいからそう遠くないこの地域に、かつて「ロシア人集落」があったことは、私もこれまで何度か耳にしている。そして、「あまり裕福ではなかった」、「自家製のジャムや酢漬け、パンを売っていた」などと聞くたびに、市内西部地区のロシア人とは別様の暮らしぶりが想像されていた。この集落の特異さは、斉藤茂吉が昭和7年の来函時に詠んだ歌からも伝わってくる。
「ロシアびと ひとかたまりに 住みつきて 街のかげなる 家等はひくし」(7首のうちの1首)
このようなおり、私は「湯の川風景」という一枚の絵の存在を昭和8年4月21日の「函館新聞」(以下、「函新」)で知った。画家の名は宮島求、草耀社なる美術グループに所属する市内の教員であった。新聞に紹介された絵は白黒で寸法も縮小されているが、そこには確かに湯川のロシア人集落が描かれている。市立函館博物館に尋ねてみたが、原作品の存在は確認できなかった。集落の様子は掲載記事中に以下のように述べられている。
「鎮守の社、湯の倉神社の裏道を登る。由緒ありげな老木の根もとに腰を下し初夏の赫熱を緑陰に遁れる。丁度ここで左右より登る来る二坂は合して更に登りとなる。人の世からおき忘れた山道、轍の跡と馬糞と朽葉の坂道は大きくうねって続いている。坂道に添ふてこれからは露人村を形成している。コバルト色のペンキを塗った素人造りの低い家屋、而も不規則な並べ方、無雑作に壁の所々を破った気まぐれな西洋窓、道南に珍しい題材である。
夏の夕べ彼等グループは各自愛妻携帯で庭先―道路ばたの草のいきれの中にテーブルを出して持寄り晩餐会に喜々として赤高い鼻を働かしている。時々三脚へ寄り来り
エカキサン、オモシロイデスカ
など愛想を振りまいている。
アレ、オクサン、サキ、コドモオカシ、ゴッソサン
今坂を上がって来た鍬を担いだ女との会話。中々ここは国際的で彼我認識充分である。」(旧漢字、旧仮名使い以外は原文のまま)
記事中で「コバルト色」と言われているのは、恐らく「明るい緑色」のことだろう。相馬久子(元函館市長登坂良作氏長女)さんの記憶によれば、湯川のロシア人の家は緑であったという。また、彼女がモスクワからサンクトペテルブルクまで旅行したおりに車窓から見た家々は「まさに湯川のロシア人の家と同じ」だったそうである。人里離れた雑木林の坂道に沿った家々。故郷の家を模したのだろう、壁はみな明るい緑一色に塗りこめられている。しかし、素人普請のせいか、梁は高く掲げられることなく、屋根はみな一様に低い。でたらめな寸法でくりぬかれた窓が、雑然とした集落からさらに統一感を奪っている。想像の中の湯川ロシア人集落は、憐れで、奇妙で、しかし、どこか牧歌的である。
第二次世界大戦後、この集落の住人はクラフツォフ、サファイロフの2家族だけとなる。そして、クラフツォフが東京へ移ってからは、とうとうサファイロフだけになる。サファイロフについては田尻聡子さんの「百万本のバラの花」(『道南女性史研究』第9号、1992年)に詳しいが、私はここで、最後の「低い緑の家」の住人の晩年を中心に、二、三の新しい知見を記しておこうと思う。
サファイロフの来函時期は(田尻さんは不明としているが)、大正7年であったらしい。昭和3年8月5日の「函新」にはサファイロフが同年8月1日付けで内務大臣から日本への帰化を認められた旨の報告があるが、そこには彼が大正7年9月に来函したと言及されている。ペトログラードからリューリ商会の会計係として極東出張中に革命となり、妻子は本国に残したまま亡命を決意したという(昭和33年8月11日「北海道新聞」(以下、「道新」)。
サファイロフの生業は、日本帰化当時はリューリ商会事務員であったが、リューリ商会の撤退後から第二次世界大戦までは化粧品の行商もした。しかし、この後は定職もなく、戦前、戦中と湯川の自宅で栽培した果実からジャムを作って生計を立てていた。戦後砂糖の配給が中断され、ジャム作りがままならなくなったとき、サファイロフは昭和23年2月15日付けで田中北海道知事に砂糖の配給を求める嘆願書を出している(「函新」昭和23年3月1日)。これに対して、同知事は彼の高齢と困窮に同情し、砂糖の代わりに水あめ10缶を配給した。この「ジャム美談」には後日談もあって、この2年後、田中知事の来函時に、サファイロフは水あめ配給の謝礼を兼ねて知事の宿泊先を表敬訪問している(「函新」昭和25年1月11日)。
サファイロフは市井のロシア語教師としても長いキャリアを持っていた。私の手元にある新聞記事では、彼が出した最も古い「露語教授」の広告は「函新」の大正13年9月22日で、この年には暮れの12月28日にも同じく個人教授の広告が出ている。翌年、サファイロフは元陸軍露語通訳寺西準一が創立した「函館露語講習会」にも講師として名を連ねている(「函新」大正14年9月15日)。
サファイロフは風変わりな老人だったのかもしれない。たとえば、道を歩いていて人とすれちがう時、絶対に自分から脇に譲ることはなかったという。次のようなエピソードもある。戦後、彼は愛犬の急死を悼み、犬を剥製に出した。ところが、できあがった剥製に生前の美しい毛並みは面影もなく、「これでは剥製にした甲斐がない」として、剥製業者の菊地某に5万円の損害賠償を求めて告訴している(「道新」昭和25年7月26日)。いずれにせよ、サファイロフは常にちょっとした有名人であった。
日本人の妻を得て、日本に帰化したサファイロフは、社会主義国となった祖国に帰る意志を持たなかった。ところが、1957年、モスクワに住んでいた長女から「お父さん、帰ってきませんか」という写真入りの手紙が届く。肉親の情が思想的相反に優ったのだろう。この手紙を受け取って以来、故国に帰り娘と逢うことが彼の悲願となる(「道新」昭和33年8月11日)。彼の帰国実現のために奔走したのが、日ソ友好協会函館支部理事長の原忠雄と棒二森屋の渡辺熊四郎社長であるが、高齢となっても行商して歩く、その「尾羽打枯らした」様子をみかねて、渡辺社長が長く彼を援助したことはあまり知られていない。
原氏は昭和33年訪ソ親善団の一員としてモスクワを訪れ、ついにサファイロフの長女、ミーリッツァ・ドシール・コーヴィチさんに会うことができた。帰国後、彼女から預かった写真をサファイロフに手渡し、彼女の近況を報告した(「道新」昭和33年10月3日)。
サファイロフの望郷の念はこれを機にいよいよ募り、また、それに共感した周囲の人々が彼の訪ソ実現に向けてさらに熱心に運動していたとき、不幸が襲う。昭和34年8月19日、サファイロフは行商中(カール・レーモンのハム、ソーセージ等を売っていたらしい)にトラックと接触し、左大腿骨骨折の重傷を負うのである。妻の入院などで、既に決定していた訪ソ予定が遅れていた矢先のことであった(「道新」昭和34年8月20日)。結局、この交通事故がもとで、サファイロフは翌昭和35年1月、訪ソを果たすことなく、94歳で函館に骨を埋めた(田尻さんは、サファイロフが永住帰国を望んだので、帰国が阻まれたと記しているが、上述の新聞によればあくまで交通事故が原因だったらしい)。
彼の死から3年後、昭和38年9月、彼の教え子でもあった市内中学教師の山田誠二さんが、日ソ協会の使節団の一員としてソ連を訪問することになった(「道新」昭和38年7月22日)。このエッセイ執筆にあたり、山田さんを探して当てて電話で伺ったところ、今から40年前、確かにサファイロフ夫人正子さんから手紙や遺品を預かり、モスクワの娘さん家族を訪ねたとのことだった。あいにく娘さん本人は不在だったので、留守番をしていたお孫さんにそれらを託してきたという。サファイロフの帰国はこうした形で実現したのであった。
歳月は流れた。現在の湯川地区に、ロシア人集落の跡を留めるものは何一つない。かつて歌人や画家の、そして市民たちの耳目を集めた「低い緑の家」は、今や、私たちの記憶や想像の片隅に残るだけである。
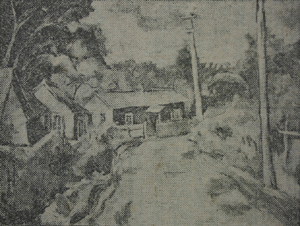
宮島求「湯の川風景」(昭和8年4月21日付「函館新聞」)
「会報」No.26 2004.9.10
「函館とロシアの交流」を読んで
前川公美夫
北海道の歴史に関心を持ってはいても、札幌に暮らしていると、ついつい目は開拓使が置かれて以降のことに向いてしまいがちである。外国との交流についても、お雇い外国人のアメリカ人を主体に眺めてしまってロシアとの交流史に特段の思いを致すことはないのだが、函館では事情は大いに違っているようだ。
函館日ロ交流史研究会創立10周年記念としての本書を読んだりペリー来航150年を迎えての活動を見聞きしたりすると、函館ではひとりロシアに限らず、アメリカや、フランス、ドイツなど、北海道が諸外国とかかわりを持ち始めたころから濃いつながりがあったという認識が、複数の世紀をまたいだ現在に至るまで、市民に潜在意識として生き続けているのだろうことを感じさせられる。それらの国の代表格としてロシアがあるのだろう。
ロシアとの交流史の研究では、水産業を軸とした経済面が主流をなすだろう。人、金、物の動きの大本には経済活動があるのだから、その背景をなす外交交渉ともども、研究の本流にあるべきことは当然である。
鈴木旭会長の巻頭言「創立10周年を迎えて」には、北洋漁業をめぐる経過が、その拠点都市としての函館市の動きを含めて分かりやすくまとめられており、本書の各論を読み進める上で大いに参考になった。菅原繁昭「ロシア(ソ連)極東諸港と函館の海運事情」も、函館が沿海州、サハリン、カムチャツカを結ぶ要の位置にあることを、歴史的経過の中で理解させてくれる。
清水恵「ロシア革命後、函館に来たロシア人」は函館が道内におけるロシア人居住の中心地であったことをまず示し、うち幾人かの例を引いてその暮らしぶりを紹介している。その内容のうち、ロシア革命後の外交史をめぐり、ソ連から函館に、正式な国交を結ぶ前から査証官が派遣されていたことが示されている。便宜的な措置であったろうが、「北洋出漁」を滞らせずに行っていこうという、両国間にあった経済活動第一の姿勢がうかがえるようだ。
その一方で、シンポジウム「大正・昭和期に函館に来たロシア人」は、経済面での交流にまして長く心に残るのが人と人とのつながりであることを理解させてくれる。「大正・昭和期」は、函館の対外交流史の中で注目が集まる幕末から明治初期にかけての時代に比べれば歴史としてはまだ新しいと言えるが、そうであったとしても、関係者が健在のうちに聞いておかなければ消え去ってしまう話が多いだろう。今やっておかなければならない仕事であった。
そうした人たちの1人として招いた女性の来し方を紹介する小山内道子「ガリーナ・アセーエヴァの歩んだ遠い道のりをたどって」は、ズヴェーレフ家の家族とその暮らしぶりを紹介することにより、函館、さらには東京のロシア人社会の様子を描き出している。
かねて、函館に限らず、当時のロシア人たちのなりわいの中で、故国の食べ物を出す飲食店のほかに衣類の行商というのを目にしたり耳にしたりしたとき、仕入れ先やお得意先はどんなところだったのだろうと、漠然と考えていた。この論考で、その背後には全国的なロシア人の輸入・行商グループがあったらしいこと、そして、ちょうど日本人の衣服が洋服に切り替わる時期に当たって商売は大きな利益を上げることができたことが示されていて、ようやく納得がいったことだった。
研究者にとって、新たな事実や観点の発掘には心が躍るものがあるだろうし、その高ぶりは読む方にも及んでくる。
原暉之「ロシアの新聞雑誌記事に見る洋式船亀田丸の事績(1861年)」の、資料4で、亀田丸がニコラエフスクに携えていった日本の商品が全く先方の関心を引かなかったこと、山田伸一「ロシア領事館前の朝鮮人座り込み」では、函館に来ていた人たちが「本州経由ではなく、朝鮮半島の東北部からロシア沿海方面を経て、海路で北海道に至っていることは、朝鮮半島と北海道の間の言わば『日本海北回り』の人の流れを示して」いたことがそうした例である。
そのほかにもまた、歴史のひとこまとして書き残しておきたい、あるいは語り継いでおきたいテーマにも心が動く。
桑嶋洋一「もう一つのロシア交流史―ディアナ号の大砲について―」は、1854年に伊豆下田港で津波に遭い、戸田村に向かう途中で沈没したディアナ号由来の大砲に関しての、函館と横浜を結んでの謎解きである。「おわりに」には、「(横浜で出てきたディアナ号の大砲が)昭和35年の発掘以来、今回まで世に明らかにされなかった理由は、横浜市が日露開国交渉と無関係だったからであろう」という嘆きとも言えそうな筆者の思いが記されているが、他面から見ると、こうしたあたりに函館の研究者の腕の振るいどころがあることを示してもいよう。
また、ところどころ現れる研究者の感想に、新聞社に身を置く者として、己を振り返ったり、共感を覚えたりするところもあった。
「ロシア極東から函館に避難したロシア人―1922年秋―」で倉田有佳は、ペトロパブロフスクからの避難民が乗った船2隻の間に起こった騒動と、その取り扱いをめぐる函館側の動きを調査し、函館日日新聞、函館毎日新聞、函館新聞に当たって記事の内容を比較しつつ全体像を探っている。
函館の歴史を調べるうえで、かつて3つの新聞が競っていたことは貴重である。それぞれの記事が内容を補い合い、また矛盾を見せてくれることを手掛かりに、より真実に近付いていくことができるだろうからである。「新聞情報を鵜呑みにしてはならず、他の資料で検証する必要がある」のはもちろんである。
当時の記者たちがそんなことを思っていたかどうかはともかく、記事は歴史を文字に刻んでいっている。いまその場にある私にとって、自分がかかわっている記事が、後世の研究者に役に立つことがあればという思いは常にある。
また、「1877年、瀬棚沖におけるロシア軍艦『アレウト号』の遭難をめぐって」で、清水恵がジョン・ウイルの回想録について、「表には出ない裏話は、逆に信ぴょう性を感じさせるものがある」と書いていることには同感するものがある。
すべてには触れられなかったが、いずれも読み応えのある内容であった。
(北海道新聞文化部長)
「会報」No.26 2004.9.10
