最後の「低い緑の家」 ―サファイロフの晩年―
清水恵
大正末期から昭和初期にかけて、湯川には一群の白系ロシア人が居住した。現在の私の住まいからそう遠くないこの地域に、かつて「ロシア人集落」があったことは、私もこれまで何度か耳にしている。そして、「あまり裕福ではなかった」、「自家製のジャムや酢漬け、パンを売っていた」などと聞くたびに、市内西部地区のロシア人とは別様の暮らしぶりが想像されていた。この集落の特異さは、斉藤茂吉が昭和7年の来函時に詠んだ歌からも伝わってくる。
「ロシアびと ひとかたまりに 住みつきて 街のかげなる 家等はひくし」(7首のうちの1首)
このようなおり、私は「湯の川風景」という一枚の絵の存在を昭和8年4月21日の「函館新聞」(以下、「函新」)で知った。画家の名は宮島求、草耀社なる美術グループに所属する市内の教員であった。新聞に紹介された絵は白黒で寸法も縮小されているが、そこには確かに湯川のロシア人集落が描かれている。市立函館博物館に尋ねてみたが、原作品の存在は確認できなかった。集落の様子は掲載記事中に以下のように述べられている。
「鎮守の社、湯の倉神社の裏道を登る。由緒ありげな老木の根もとに腰を下し初夏の赫熱を緑陰に遁れる。丁度ここで左右より登る来る二坂は合して更に登りとなる。人の世からおき忘れた山道、轍の跡と馬糞と朽葉の坂道は大きくうねって続いている。坂道に添ふてこれからは露人村を形成している。コバルト色のペンキを塗った素人造りの低い家屋、而も不規則な並べ方、無雑作に壁の所々を破った気まぐれな西洋窓、道南に珍しい題材である。
夏の夕べ彼等グループは各自愛妻携帯で庭先―道路ばたの草のいきれの中にテーブルを出して持寄り晩餐会に喜々として赤高い鼻を働かしている。時々三脚へ寄り来り
エカキサン、オモシロイデスカ
など愛想を振りまいている。
アレ、オクサン、サキ、コドモオカシ、ゴッソサン
今坂を上がって来た鍬を担いだ女との会話。中々ここは国際的で彼我認識充分である。」(旧漢字、旧仮名使い以外は原文のまま)
記事中で「コバルト色」と言われているのは、恐らく「明るい緑色」のことだろう。相馬久子(元函館市長登坂良作氏長女)さんの記憶によれば、湯川のロシア人の家は緑であったという。また、彼女がモスクワからサンクトペテルブルクまで旅行したおりに車窓から見た家々は「まさに湯川のロシア人の家と同じ」だったそうである。人里離れた雑木林の坂道に沿った家々。故郷の家を模したのだろう、壁はみな明るい緑一色に塗りこめられている。しかし、素人普請のせいか、梁は高く掲げられることなく、屋根はみな一様に低い。でたらめな寸法でくりぬかれた窓が、雑然とした集落からさらに統一感を奪っている。想像の中の湯川ロシア人集落は、憐れで、奇妙で、しかし、どこか牧歌的である。
第二次世界大戦後、この集落の住人はクラフツォフ、サファイロフの2家族だけとなる。そして、クラフツォフが東京へ移ってからは、とうとうサファイロフだけになる。サファイロフについては田尻聡子さんの「百万本のバラの花」(『道南女性史研究』第9号、1992年)に詳しいが、私はここで、最後の「低い緑の家」の住人の晩年を中心に、二、三の新しい知見を記しておこうと思う。
サファイロフの来函時期は(田尻さんは不明としているが)、大正7年であったらしい。昭和3年8月5日の「函新」にはサファイロフが同年8月1日付けで内務大臣から日本への帰化を認められた旨の報告があるが、そこには彼が大正7年9月に来函したと言及されている。ペトログラードからリューリ商会の会計係として極東出張中に革命となり、妻子は本国に残したまま亡命を決意したという(昭和33年8月11日「北海道新聞」(以下、「道新」)。
サファイロフの生業は、日本帰化当時はリューリ商会事務員であったが、リューリ商会の撤退後から第二次世界大戦までは化粧品の行商もした。しかし、この後は定職もなく、戦前、戦中と湯川の自宅で栽培した果実からジャムを作って生計を立てていた。戦後砂糖の配給が中断され、ジャム作りがままならなくなったとき、サファイロフは昭和23年2月15日付けで田中北海道知事に砂糖の配給を求める嘆願書を出している(「函新」昭和23年3月1日)。これに対して、同知事は彼の高齢と困窮に同情し、砂糖の代わりに水あめ10缶を配給した。この「ジャム美談」には後日談もあって、この2年後、田中知事の来函時に、サファイロフは水あめ配給の謝礼を兼ねて知事の宿泊先を表敬訪問している(「函新」昭和25年1月11日)。
サファイロフは市井のロシア語教師としても長いキャリアを持っていた。私の手元にある新聞記事では、彼が出した最も古い「露語教授」の広告は「函新」の大正13年9月22日で、この年には暮れの12月28日にも同じく個人教授の広告が出ている。翌年、サファイロフは元陸軍露語通訳寺西準一が創立した「函館露語講習会」にも講師として名を連ねている(「函新」大正14年9月15日)。
サファイロフは風変わりな老人だったのかもしれない。たとえば、道を歩いていて人とすれちがう時、絶対に自分から脇に譲ることはなかったという。次のようなエピソードもある。戦後、彼は愛犬の急死を悼み、犬を剥製に出した。ところが、できあがった剥製に生前の美しい毛並みは面影もなく、「これでは剥製にした甲斐がない」として、剥製業者の菊地某に5万円の損害賠償を求めて告訴している(「道新」昭和25年7月26日)。いずれにせよ、サファイロフは常にちょっとした有名人であった。
日本人の妻を得て、日本に帰化したサファイロフは、社会主義国となった祖国に帰る意志を持たなかった。ところが、1957年、モスクワに住んでいた長女から「お父さん、帰ってきませんか」という写真入りの手紙が届く。肉親の情が思想的相反に優ったのだろう。この手紙を受け取って以来、故国に帰り娘と逢うことが彼の悲願となる(「道新」昭和33年8月11日)。彼の帰国実現のために奔走したのが、日ソ友好協会函館支部理事長の原忠雄と棒二森屋の渡辺熊四郎社長であるが、高齢となっても行商して歩く、その「尾羽打枯らした」様子をみかねて、渡辺社長が長く彼を援助したことはあまり知られていない。
原氏は昭和33年訪ソ親善団の一員としてモスクワを訪れ、ついにサファイロフの長女、ミーリッツァ・ドシール・コーヴィチさんに会うことができた。帰国後、彼女から預かった写真をサファイロフに手渡し、彼女の近況を報告した(「道新」昭和33年10月3日)。
サファイロフの望郷の念はこれを機にいよいよ募り、また、それに共感した周囲の人々が彼の訪ソ実現に向けてさらに熱心に運動していたとき、不幸が襲う。昭和34年8月19日、サファイロフは行商中(カール・レーモンのハム、ソーセージ等を売っていたらしい)にトラックと接触し、左大腿骨骨折の重傷を負うのである。妻の入院などで、既に決定していた訪ソ予定が遅れていた矢先のことであった(「道新」昭和34年8月20日)。結局、この交通事故がもとで、サファイロフは翌昭和35年1月、訪ソを果たすことなく、94歳で函館に骨を埋めた(田尻さんは、サファイロフが永住帰国を望んだので、帰国が阻まれたと記しているが、上述の新聞によればあくまで交通事故が原因だったらしい)。
彼の死から3年後、昭和38年9月、彼の教え子でもあった市内中学教師の山田誠二さんが、日ソ協会の使節団の一員としてソ連を訪問することになった(「道新」昭和38年7月22日)。このエッセイ執筆にあたり、山田さんを探して当てて電話で伺ったところ、今から40年前、確かにサファイロフ夫人正子さんから手紙や遺品を預かり、モスクワの娘さん家族を訪ねたとのことだった。あいにく娘さん本人は不在だったので、留守番をしていたお孫さんにそれらを託してきたという。サファイロフの帰国はこうした形で実現したのであった。
歳月は流れた。現在の湯川地区に、ロシア人集落の跡を留めるものは何一つない。かつて歌人や画家の、そして市民たちの耳目を集めた「低い緑の家」は、今や、私たちの記憶や想像の片隅に残るだけである。
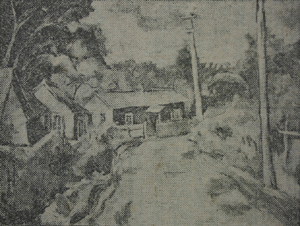
宮島求「湯の川風景」(昭和8年4月21日付「函館新聞」)
「会報」No.26 2004.9.10
